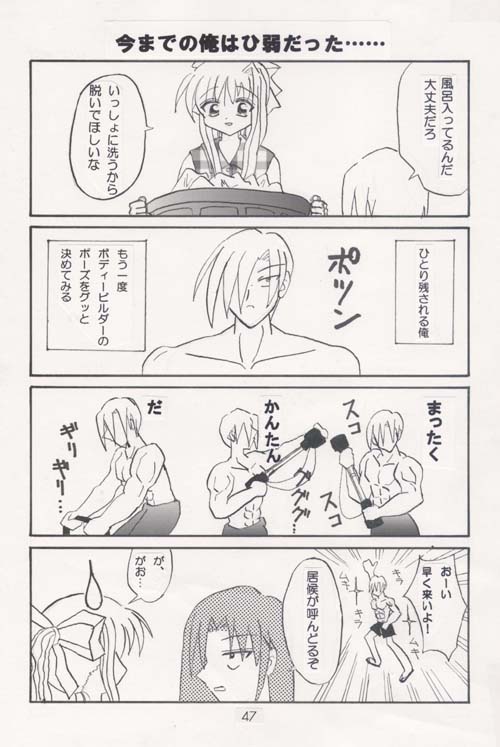残夏 〜神尾晴子〜
藤沢優
「決めた。あの子をうちの子にする」
そう決めた次の日には、うちはバイクに飛び乗っていた。
ヘルメットから覗く髪が風に舞う。目の前を伸びるバイパスを限界まで跳ばすと、エンジンは助けてくれといわんばかりに悲鳴を上げる。それでもうちは速度を緩めずスロットルを握る。
うちの住む街から、二時間程バイクを走らせた少し大きな街に目的の家はある。その住宅街でも一際目立つ日本家屋の豪邸の前に立つ。
門の表札には『橘』の文字。
観鈴、待っときや。話をつけて直ぐに戻るからな。
重厚な造りの門の呼び鈴を押す。一瞬遅れて鐘の音が家の中に響く。
しばらくして備え付けのインターホンから応答があった。
『はい、どなた様ですか?』
インターホンを通して微妙に機械変換された無機質な声。恐らくお手伝いさんだろう。
「神尾です。神尾晴子です。御無沙汰しています」
今すぐにでも玄関を突き破って入りたい気持ちを、すんでの所で抑えながらうちは答える。
『…御用件は何でしょう?』
「観鈴の事で話したい事がありまして」
『しばらくお待ち下さい』
しばらく沈黙が続く。やがて
『誠に申し訳ありませんが、大旦那様はお会い出来ません。今日はお引き取り下さい』
無感情に無常な答え。でもそれは半ば予想していた返事。
「そうですか…でしたら、会えるまでここで待たせてもらいます」
そう言うとうちは橘の家の門前に座り込む。持って来た荷物と履いていたパンプスを脇に置き、軽く埃を掃って正座する。
夏の陽射しに焼かれた道路の熱がストッキング越しに伝わってくる。
陽射しを遮る影もなく、夏の刺す様な太陽が肌を焼く。汗が染み出しゆっくりと流れ、落ちる。
往来の眼があからさまに奇異の視線を投げかけてくるのが分かる。でもそんな事はどうでもいい事だった。
観鈴、待っときや。話をつけて直ぐに戻るからな……
何度も何度も胸の中で繰り返す。
…座り込んでからどれ位経っただろう?二時間?三時間?半日?
朦朧とした意識で脛に触れると、所々皮膚が破れそこから血が滲んでいた。更に陽射しで熱せられたアスファルトが傷口を焼いている。
針を突き刺す様な激痛と灼熱の陽射し、そして心に絡み付くいつ終わるとも知れない不安に倒
れそうになる。
その時、門の横の勝手口が開いた。出て来たのは少し陰のある若い男。
「はぁ…君も強情だね」
呆れたような口調でその男、橘敬介は言う。
「それだけが取り柄やからな、若旦那」
「その呼び方は止めてくれないか…」
言いながら敬介は肩をすくめる。そして足元に視線を落とす。
「おい、足から血が出ているじゃないか」
「女は血なんて見慣れてる。月一の事やからな」
うちは残された精神力で精一杯の虚勢を張る。
「そうかもしれないが」
でも敬介は、うちの虚勢をかわす様に淡々と答えた。
「あんたなぁ、真面目にかえしなや。こっちが恥ずかしなるやろ」
「…すまない」
謝ると敬介はうちの横にしゃがみ込む。
「何や?付き合うてくれるんか?」
でも敬介はうちの言葉を無視すると、聞き分けのない子供をなだめる様に、それでいて有無を言わせぬ口調で言った。
「…僕と橘の家の身勝手なわがままで君には迷惑をかけた。その点については謝るし、感謝もしている。でもどれだけ君が主張しても法的には、神尾観鈴は僕と郁子の子なんだ。そしてこの橘の家を継ぐ後継者でもある。それは分かって欲しい…それに君と観鈴は所詮血の繋がっていない他人だろう」
その言葉を最後まで聞かず、うちは敬介の頬を思い切り叩いていた。
「…痛いじゃないか」
「所詮ってなんや!あんたは何も分かってへん!あの子は…観鈴は神尾郁子の娘、そしてこの神尾晴子の娘や!誰が何言おうと!」
流れる涙と染み出す汗で顔をくしゃくしゃにしながら訴える。
「一度は観鈴を捨てた人間が分かったような事言うな!」
頬をおさえながら敬介は呆然となる。『観鈴を捨てた』という言葉に、一瞬敬介は肩を震わせた。
「……晴子…家に上がってくれ」
敬介は立ち上がるとうちの目を見てそう言った。
「話、聞いてくれるんか!」
「あくまで聞くだけだ…それにこれだけ奇異の目で見られると橘の家としての体裁が悪い」
周りを見回しながらそう言うと、敬介はうちに手を差し伸べる。
うちはこの時、ああこれから新しい時間が始まるんや、と信じて疑わなかった。でもその差し伸べられた手こそ本当は終わりへの序曲だったのだ。
それに気が付いたのは、全てが終わってからだったけど。
† † †
陽の昇っている時間が目立って短くなってきた九月。
少し前までならまだ陽射しを感じられたのに、今は見上げると空には星が瞬き始め、少しずつ街が眠りに落ちていこうとしていた。それでも絡み付く様な熱気は夏の夜とあまり変わらない。
陽の光よりも、街の人工的な明かりが多く地上を照らし始める。
その明かりの中を、一際鋭い灯りが駆け抜ける。
「今日もバイク調子ええわ!うちとは大違いや…」
うちは午後からの仕事を早目に切り上げると、家に戻るためにバイクを走らせていた。元々今の仕事はもう辞めるつもりで、上司にも了承を取ってある。残務整理がまだ残っているが、今までの様に夜中まで居残る必要はもうない。
だが待つ人間のいない我が家に急いで帰る必要もないので、バイクの速度は抑え気味に走る。
今までなら勢いに任せて突っ込んでいた納屋の前で一旦停止し、手で押して中に停める。
「ただいまや〜……って言っても誰もおらんか」
静まり返った家に入るとうちは家中の電気を点ける。
自分の部屋。廊下。台所…
もういない筈の人影を追う様に全ての電気のスイッチを押していく。
そして最後に居間の電気を点けた。一瞬遅れて点いた明かりに映るのはいつもとかわり栄えのしない風景。
うちはその風景の片隅に声をかけた。
「観鈴、帰ったで。一人寂しなかったか?」
そこにあるのは笑顔の観鈴の遺影。うちの声だけが家の中に空しく響く。
そして、その言葉は恐らくうち自身に対する問い掛け。
仕事用のスーツを脱ぎ捨て普段着に着替える。直ぐに台所に向かい、日本酒の瓶とコップを持ってくる。溢れんばかりの勢いで酒をコップに注ぐと一気に飲んだ。味なんて感じなかった。
もう一杯注ぐ。そしてまた一気に流し込む。無謀な飲み方だとは分かっている。でも、それを注意してくれる人間はもうこの家にはいない。
観鈴――
郁子姉ちゃんの一人娘。姉ちゃんは元々体が弱いのに、好きな男と駆け落ち同然に家を飛び出していった。姉ちゃんが好きになった男、橘敬介はこの地方では結構名の知れた名家の跡取り息子。だからもちろん橘の家が一介の庶民である神尾家の娘との交際を認めるはずもなく、一緒になる事を大反対した。それでも二人は、愛と若さに任せて遠くの街で新婚生活を始めた。そしてふらっと届いた手紙で、子供が出来た事を知った。
幸せに暮らしとるんや、幼心にうちはそう思った。
でもその時、姉ちゃんの体は既に病に蝕まれていた。観鈴を生んだ直後に病で倒れたという。
それから十年、姉ちゃんは亡くなった。
その頃合を見計らってか、橘の家は敬介を半ば強引に家に引き戻そうとした。他の良家の娘とお見合いをさせるために。
そして橘の家にとって当然観鈴は邪魔な存在だった。
案の定、家に帰る直前ふらりと現れた敬介はうちにこう言った。
『僕は橘の家に戻る。でも観鈴は連れて行けない。そこで悪いがいつか迎えに来る時までこの家で観鈴を預かってくれないか』と。
身勝手な言い草やと思った。高校を卒業して、直ぐに両親を亡くし一人途方にくれている十八歳のうちに十歳の子供を押し付けるなんて。
ふざけんな!自分らのケツは自分らで拭かんかい!うちは知らん!
そう言いたかった。でも、言えなかった。
敬介の陰に隠れていたその子の瞳があまりにも姉ちゃんに似ていて、気がつくとうちはこう言っていた。
好きにしたらええわ、と。
その言葉に敬介は頭を下げると、細長い分厚い封筒を差し出した。
うちはその中身を見て『アホにすんなっ!うちは乞食か!』ってあいつの顔に投げ返した。それ以来あいつはうちの家に来ていない……
正直、観鈴を最初見た時にうちは、不安と苛立ちと共に嬉しさもあった。姉ちゃんが出て行って、そして両親まで亡くして天涯孤独になったうちにまた家族が出来たのだから。それも姉ちゃんによく似た可愛らしい女の子。
あれから十年、うちは観鈴と暮らして来た。
色々あった。苦労した。泣きたくもなった。でも楽しかった。
でもそんな幸せな毎日が、ある夏の日にかかってきた一本の電話で脆くも崩された。橘の家でどんな事があったのかは知らないが、いきなり観鈴を引き取りたいと言ってきた。
観鈴をなくしたらうちはホンマに天涯孤独になる、そう思ったうちは猛反対した。文字通り命を賭けて話し合いもした。
「その結果がこれか…」
微笑む観鈴の遺影を見てうちは呟いた。そしてさして広くはない居間から家の中を見回す。
観鈴が小さい頃からの身長を記録してきた柱の傷。
観鈴が悪戯した時に閉じ込めてた押し入れ。
観鈴がよう立って料理していた台所。
観鈴が洗濯物を干していた庭。
観鈴が、観鈴が……
ああ、この家には思い出が多過ぎるわ。
「あかん!この家で一人飲んでたら余計寂しくなってくる」
コップに残っている酒を一気に喉に流し込むと、うちは立ち上がる。
「外行こ」
鞄に入れていた財布をGパンのポケットにねじり込む。その時、視線の隅で何かが光った。
「…そや、あんたも一緒に行くか?」
うちはそれを摘み上げる。それは昼間、観鈴のクラスメイトの茂美ちゃんが旅行のお土産にと持ってきた星の砂の子瓶。その輝きに魅せられて、うちは無意識に子瓶をポケットに入れた。
玄関を出ると、まとわりつく様な湿気が体を舐める。うちは湿気から逃げる様に足早に商店街へ向かう。体中が冷たいものを欲していた。
夜の帳に包まれた商店街は既に半分ほどの店がシャッターを下ろしていた。開いている店も客の姿は殆どない。うちは人気のない商店街を抜け、目的の店を目指す。
この商店街の端にはこの街では数少ない飲み屋がある。その店は漁協から新鮮な魚を仕入れて美味い料理を出す事で評判の居酒屋だ。目的の店の前に立つ。勢い良く店の戸を開けると、そこには意外な先客がいた。
「霧島…先生…」
目の前のカウンター席に座っていたその先客は、この街唯一の医療機関、霧島医院の女医さんだった。確か名前は霧島聖先生だったか?
先生は腰まで届く艶やかな髪で、その涼し気な瞳に艶かしい唇が妖艶と形容するに相応しい美女。女のうちから見ても惚れてしまいそうな魅力的な女性だ。
「ああ、神尾さん。こんばんは」
「こんばんは…先生もこんな所でお酒飲むんやね…」
「医者も人間ですよ、お酒くらい飲みます」
そう言って微笑む。その笑みは女のうちから見ても本当に綺麗で、それでいてどこか儚い印象を受けた。
|